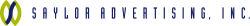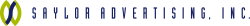「これからはスマホ優先だよね!」スマホファーストの正しい解釈の仕方
Web・デジタルプロモーション
スマートフォンの著しい普及で、「モバイルファースト」から「スマホファースト」という言葉が出現し、とにかくスマホ第一優先で考えないといけない、といった話をよく聞きます。
確かに、様々な業種(主にBtoC)のアクセス解析をみると、モバイル(スマホ)の割合が少なくとも半数を超えています。
2011年頃からスマホ需要が右肩上がりで、その頃はまだPCサイトが主流でしたが、徐々に何らかのスマホ対策をしています。
スマホ対策のパターン
「何らかのスマホ対策」にはいくつかパターンがあります。
- PCサイトは残しておき、主要なコンテンツだけスマホページを追加
- 現状PCサイトのヘッダーやサイドメニュー、文字の大きさ等を画面幅で調整し最適化
- フルリニューアルのタイミングでレスポンシブウェブデザイン
上記の1と2は「スマホファースト」というより、「とりあえずスマホ」という対策です。
3は「スマホファースト」として最適な方法だと思います。
オリジナルのデザインで一から作っていく場合と、コストを極力抑えるために、あらかじめPC、スマホ、タブレットに最適化されるレスポンシブウェブデザインのテンプレートを用い、画像や文字を当てはめていけば、見栄えの良いホームページが完成するというシステムがあります。
いずれの方法にしても、肝心なのはユーザーの行動を意識した作り方です。
スマホファーストの解釈
以下のどちらの考え方で取り組むべきでしょうか。
スマホファースト=スマホユーザーが多いからPCより優先
スマホファースト=スマホを閲覧している人の状況・行動を考えた設計
スマホの利用シーンだけでなく、購買行動においての心理思考、商品やサービスの特性(検討期間の長さや比較検討の数等)は、商品やサービスによって多種多様です。
- ビジネスマンが外出先でサービスを予約
- 主婦がテレビを見ながらスマホで商品を比較検討し資料請求
- 友達同士外出先でお店を探し、電話予約
- 通勤時にスマホで比較、家に帰ってからPCで詳細を見てじっくり検討
ユーザーに何らかの行動を起こしてもらうことがサイトの役割だとすると、どういった作りにすれば反応が得られやすいかを考えなければなりません。
PC閲覧とスマホ閲覧、それぞれにおいてスマホユーザーの行動を考えた上で、例えば、スマホではアクションを起こしやすく、PCでは様々な要素が一覧で見えてじっくり検討できるようなデザイン設計とし、PCのトップページでは第2階層にあるコンテンツの表現を工夫しバナーを設置するなどの手法も考えられます。
これからリニューアルをする場合は、現状、スマホでアクセスしてきた場合に閲覧されやすいページとされにくいページを把握し、こちらの意図通りにユーザーが行動を起こしているかどうか確認します。
ただし、BtoB企業の場合は、スマホよりPC利用が多いケースもあります。
まずは、現状の見極めが大切です。